飲食店を失敗しない、5つのチェックポイント part4-1

飲食店を失敗しない、5つのチェックポイントを確認
前回Part3の冒頭で説明しましたとおり、以下が飲食店を失敗なく経営するための、5つの項目です。
1、より多くの人が食べたいと思う料理を提供できること
2、それが美味しい料理であること
3、お店全体でここちよいサービスが提供できること
4、手ごろな料金であること
5、おおぜいのお客様がお見えになりやすい場所で営業すること
前回にひき続き今回は
4、「手ごろな料金であること」①について
「手ごろな料金」とは、どれくらいの料金を言うのでしょうか。今は、通常、安い、手軽なと言う意味で使われています。つまり、そのお店の料理やサービスに対して、お客様が求めやすい価格、リーズナブルだと感じる価格です。
食事を終えて、お会計の際に、「何だこの店、高いなー!」とか、「わりとリーズナブルだったねっ!」など、何かしら感じるものです。
「あまり美味しくないし、評判ばっかりで高いなー。」と思ったお店には、有名店でも2度は行きたくありません。
逆に季節感を感じられる、新鮮な食材を使った美味しい料理を、気持ちよいサービスでいただけたら、多少高くても、「いい料金だけど、これだけ満足すれば、たまにはいいね。」とリピーターになっていただけるチャンスです。
大切なのは、具体的な価格の中身の問題です。
その料理の内容だけでなく、サービスも含めて全体が、提示された金額に「見合ったもの」、または「ふさわしい」金額であれば、誰も高いとは思いません。
では、どういう「中身」が必要なのか。それは、お客さまが何を期待してその店に行くかということで、変わります。
「美味しい料理」「サービス」について詳しくは、この記事のシリーズ、Part2,Part3を参考にしてください。
個人店舗、専門店、大手ファミレス、ファストフード、屋台など、お客様が、何を期待して利用するのでしょう。それは、お客様の目的です。
・ただのビジネスランチのため
・ゆっくり友人と美味しい料理とお酒で、くつろぐため
・美味しい焼肉を食べたいから
・たまの休日に家族で夕食
・旬の魚が食べたい
いろいろな動機あるいは目的があります。
各々の場にふさわしい、料理とサービスが提供できれば、問題ありません。
・ビジネスランチでも、お昼にサッと食べてすぐ仕事にもどりたいのに、料理がなかなか出てこない。長時間またされたら嫌ですね。
・ゆっくり友人とくつろいで、美味しいものでも、と思って和食の高級店に入ったのに、季節はずれの料理や、スタッフの態度が悪るかったりしたら、楽しくないですね。
・美味しい焼肉をもとめて、高級な焼肉店にはいったのに、輸入肉がメインだったり、冷凍肉が凍ったまま皿に盛られてたら、違うなーと思います
・子供もいっしょに、家族で食事に行ったのに、子供が頼んだものが、なかなか出てこないので、子供がぐずりだす。困ります。
・お寿司屋さんに行って、季節感を味わいたいと思ったが、出てきたのは、季節はずれの魚に、冷凍を戻したものばかり。
このようでは、仮にいくらか安くても、納得いきません。
料理、サービスの中身がともなわないと、リーズナブルとは言えません。
手ごろに見える料金設定だけど、実は「安いけれど、料理が不味い、質が低い」店、「安いけれど、いろいろなサービスの状態が悪い」店、どちらもこまりものです。
「手ごろな料金」は、料理とサービスのトータルで判断されます。
いくつか例をあげて、詳しく説明します。
ファミリーレストランなどのチェーン店について
「お手ごろ価格」で注意しておきたいのが、大手ファミレスなどのチェーン店です。
私は知人の紹介で、1年半と短期間でしたが大手ファミレスの厨房で、お手伝いをさせていただいた経験があります。大変勉強になりました。
売上高で言えば、レストランも居酒屋も、今やこの業態が飲食業界のトップを占めています。
個人店舗は、この業態の店には、価格で競争をしてもかないません。店舗サイドからしか見れませんでしたが、すべてが確実に利益がでるように、無駄なく超合理的に計算されつくされて設計されています。ノウハウの結集みたいなものです。
仕入れ
仕入れは、独自ルートがあります。生産者から直接と言うルートもあります。かなり安く仕入れます。
料理
料理は、セントラルキッチンと言う、巨大な工場を持っているか、あるいは、下請けの食品会社を傘下に、そこで料理を半完成品または、すぐに提供できる完成品まで加工してしまいます。それを各店舗で仕上げたり、盛り付けたりします。
このように、たいへん合理的にできますので、個人店舗ではどうやっても、たちうちできないほどに、原価を低くおさえる事ができます。
内装など
内装などのハードな面も、専属の内装会社があります。通常よりかなり、安価にスピーディーに工事ができるシステムをもっています。
その他
店舗開発、サービス、教育、などソフト面でもシステム化されて、常に新情報とともに更新されるマニュアルにもとづき、合理的に実施されます。
対策
ではどうしたらいいんでしょうか。
チェーン店にはない、個人店の魅力をアピールすることです。価格は、全体的に店の利益が確保できるような「お手ごろ価格」を調整する。また、本当に手作りの、美味しい料理を作っていれば、多少は高くても、お客様はお越しくださいます。
先ほど言いましたが、工場で生産した製品と、料理人が、一品づつ作る料理は、見た目こそ似ていますが、全く別のものと考えていいでしょう。二つならべて食べれば、明らかに判別がつくでしょう。また、差がつくように作れなければ、いけません。
では具体的にどうすれば、差別化できるのか。
・なるべく新鮮な食材を使う。古い食材は、使わない。
古ければ、味も栄養もそこなわれます。
・冷凍食品や保存食品は最低限度にする。
肉や魚も含めて、冷凍食品を使用することには、賛否両論あります。
私の考えですが、日本は小さな島国で、四季おりおりの野菜でも魚介類でも新鮮な食材が、すぐ手がとどく近いところに、豊富にあります。天災でもなければ、毎日手に入ります。
しかも輸送機関などのインフラも完備されています。こんな好条件の土地にいるのに、なにも冷凍したり、保存したりした古い食材ばかりを、お金をいただいて、大切なお客様におだしするのは、どうかと思います。
冷凍でしか入手できない食材もありますが、必要最小限度にしましょう。
冷凍などの保存食は、一度に食べきれないほどの多くの農作物や魚介類などの食材が、手に入ったときの臨時の保管方法ではないんでしょうか。
ご家庭で、食材の安売りでたくさん買って冷凍保存するのとは、ちょっと意味が違う気がします。
・四季おりおりの食材を使用し、日々こまめに変化をもたせ、季節感を楽しく、味わっていただく。お客様をあきさせない。
・出汁やスープもできるだけ、インスタントの粉や濃縮の液体のものを使わず、素材から吟味して毎回、自店で作る。
食材の仕入れ先の店舗に行くと、調味料の棚には、醤油、味噌等の隣に、インスタントの食材や粉末エキスや、缶詰のソースやスープ類と各種化学調味料系の材料がところせましと並んでいます。
こういったものを使えば、楽でいいんですが、せめて基本となるスープや出汁、ブイヨンくらは自分で一から作っていただきたい。個人店では、それがお店の味になるんですから。
それには時間も労力も、経費もかかりますが、いろいろな料理の基礎になるものです。鶏の風味が必要な料理なら、ガラからとればいい。牛のスープなら、牛骨や筋からとればいい。ホタテの風味が欲しければ、ホタテを使えばいい。
「命の出汁」とはよく言ったものです。お店の料理にとってはまさに「命」です。
いろいろの形態のお店がある中で、個人店舗が生き残る道は、「本物志向の店」です。
ファミレス、ファーストフードという業態が台頭して久しくなります。彼ら自体も苦しんで、いろいろと業態を時代にあわせて変化させています。
ずっと安定して同じスタイルで何十年も存続しているわけではありません。ファミレスや各種チェーン店どうしでも、激しい競争が、繰り返されています。
この競争の中で、われわれ個人店舗が生き延び、繁盛していくには、大手チェーンにはできないことを狙わなければなりません。
インスタントではなく、本物志向を提案します。そうしてこそ、「お手ごろの価格」として、お客様は納得し、気持ちよくお支払くださることでしょう。
今回は、この辺で失礼します。次回は、同じテーマで「手ごろな料金であること」②として、個人店舗の事例をあげて説明します。


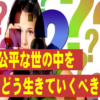







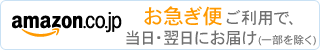
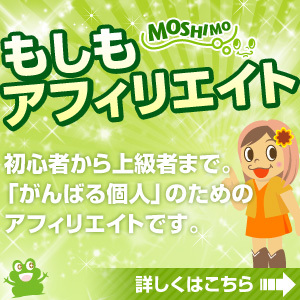


最近のコメント